
daily dose of research
Anti-Bias Curriculum: Tools for Empowering Young ChildrenDerman-Sparks
1989
Showcases research and case studies at implementing anti-bias curriculum in the classroom.
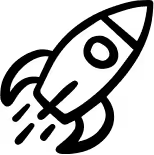
featured contributor
Matthew Byars
幼少期おめでとう、教育関係者の皆さん
学びと成長に満ちた夏を過ごした後、私は11年目に教室に戻りました。私は新しいアイデアと、敏感な共感の魂を守るために厚みのある防具一式と、もちろん無条件の愛に満ちた心で武装していました。初日にシラバスを調べる計画を断念し、代わりに学生に一連のステーションに参加させて、一日の単調さを打ち破り、座って行動する機会を与えることにしました。
これらのステーションの1つに、学生が自分自身に関する情報を記入するための「ミートミー」アンケートが含まれていました。これについては後ほど説明します。
私はドアの前に立った。そのドアはシップラップの紙で覆い、「こんにちは、今日誰も言わなかった場合に備えて。私はあなたを信じている。君はここに属している。」生徒一人ひとりに笑顔で「おはよう!」と熱意を持って挨拶しました。誰も返事をしてくれなかったが、私はただ待つしかないと思った。私は毎回、いつものエネルギーで授業を始めましたが、テクノロジーが私たちに有利に働かなかったためにステーションを捨てなければならなくなったときも、慌てることはありませんでした。鉛筆をつまずいてiPadのカートを丸ごと学生団の前の廊下の床に捨てても、私は怒ることすらありませんでした。ベルの後、生徒たちが静かに教室を出て行っても、「良い一日を!」という私の陽気な声を無視して、ずっと満面の笑みを浮かべていました。私は心の鼓動ひとつに、出会った生徒一人ひとりに会い、愛と興奮だけを醸し出そうとしました。
2日目に生徒とゲームをし、生徒が始めた性格評価を終わらせるようにしました。そうすれば、彼らの「ミートミー」アンケートの回答に目を通し、初心者のことを知り、先輩が昨年からどのように進化してきたかを見ることができました。
最初の調査はほとんど空白でした。
奇妙だと思ったけど、それは私を驚かせなかった。技術的な問題がいくつかありました。この学生は時間に追われていたのかもしれません。
2回目の調査はほとんど空白でした。そして三回目。そして4番目。
5番目の人は、ニックネームを入れた場所を除いて、すべての回答で「わからない」と言いました。
10人目は、「死んだほうがましだ」と言いました。
23人目は、「学校は子供の頃の喜びを打ち負かすための道具に過ぎない」と言いました。
次々と、「学校は最悪だ」、「これは嫌だ」、「寝たい」、「ここでは決して幸せではない」という多くを除いて、ほとんど空白の調査が続きました。
「好きな科目はありません。」
「ここの誰も本当に気にしない。」
「私は本を読まないし、あなたは私を作ることができない。」
111件の調査の後(私には127人の学生がいるので、他の生徒がどうなったかは誰にもわかりません)、ラップトップを閉じて目を閉じました。今年は自分の仕事が途切れることはわかっていましたが、こんなに悲惨な状況になることはもうあり得ませんよね?
私は親友の先生に助言を求めた。彼女は、彼らが初日に「あなたのことを知る」ことをやりすぎたのかもしれません。それが努力不足とネガティブさの原因だったのかもしれません。
それで、3日目、私はクラスの前に立って、何が起こったのか尋ねました。「アンケートに答えた回数が多すぎましたか?」
サイレンス。彼らは首を横に振った。「いいえ」と誰かが口を揃えました。「あなたのものだけでした。」
「私が読むつもりはないと思っていましたか?」
うなずきます。ほとんど真っ白な視線。もっと沈黙。
もう一度やってみた。「そんなに学校が嫌いなの?」
「うん」の響き渡る合唱が私を怒らせた。
私は立ち止まり、それからこう言いました。「本当にごめんなさい。長い間、学ぶ喜びを奪われてしまって、本当に残念です。
私たちはもう少し話をしてから、本のスピードデート活動に移り、彼らが自分で読み物を選ぶことができるようにしました.私は3日目に建物の外に出て、その日の仕事については満足していましたが、彼らの信頼を得て、私の教室に本当に人間らしさを取り戻すにはどれくらいの時間がかかるのだろうかと思いました。
しかし、4日目に小さな太陽光線が通り抜け始めたとき、私の上にかかっていた雲は消えました。今回、私が部屋の外で足の付け根を跳ねながら立って、各生徒がドアを通り抜けるのを見て本当に興奮していたとき、お返しに多くの生徒が私に挨拶してくれました。実際、多くの学生は、普段はわざわざそうしない学生でさえ、廊下で私に笑顔で「こんにちは」と言ってくれました。
雰囲気は最初の3日間とはまったく違った感じがしました。学生たちはより社交的で、笑顔も増えました。ノートをセットアップしたり、はさみやテープを分け合ったり、スティックのりをお互いに渡したりする作業をしていると、活気が溢れていました。部屋中をうろうろしながら紙くずを集めてリサイクルしたところ、心から感謝の気持ちが伝わりました。何人かの学生が立ち止まって私と会話を交わしました。そのうちの一つのグループは実際に私のアドバイスを求めていました。ベルが鳴ると、ほとんどの生徒が私に良い週末を過ごしてほしいと願ってくれました。そのうちの一人が私を「ママ」と呼んだ。
その夜のフットボールの試合で、2年前に卒業した元学生に会いました。「ねえ」彼は言いました。「兄は、今のところあなたのクラスだけが好きなクラスだと言っています。」
たぶん金曜日だったのでしょう。あるいは、もしかしたら、私が与えなければならないすべての愛を彼らが受け入れてくれるのをそれほど長く待つことはないかもしれません。